

もう、カーボンの特別感は全くないね

自由な形でにきるのがカーボンだけど、結局みんな同じデザイン
逆に、スチールフレームの方がインパクトが大きい。
ぶっといフレームばかり見ていると、スチールフレームのすっきりした見た目が新鮮。
自転車は100年前からほとんど形を変えていない。
競技が誕生してからの間、ほとんどの時代で活躍してきたのはスチールフレーム。
長い間、競技の最先端機材であったスチールフレームは、現代では通用しないのか。
いや、そんなことはない。
ホビーレーサーにとって、機材の影響なんてほんの僅か。
その僅かな性能差をプラセボ効果で大きく感じる。
そして、機材の話に花が咲く。
趣味レベルだったら、速い人は何に乗っても速い。
実際、プロ選手でもそう。
クロモリからカーボンに変えると、アタックをバンバン決められるとか、そんなはずはない。
あれだけ価格と形状が違うなら、もっと速く走れたり、楽になってほしい。
(実はスチールフレームだからといって安いわけじゃないけど)
でも、実際はカーボンに乗っていても、速くはなれない。
だとしたら、フレーム選びの視点を変えてみてはどうだろうか。
スチールなら、フルカスタムが可能。
逆に言えば需要が減って、在庫商品がないといってもいい。
カタログから選んでパッと買えないのが今のスチールフレーム。
カスタムフレームは、勉強しないと注文すら戸惑う。
フレームビルダーが自分のためだけに作ってくれるなんて、まさに男のロマン。
それにそんな乗り物って、なかなかない。
大量生産品に囲まれて生活している中、
フルカスタムのクロモリフレームはめっぽう愛着が沸く
クロモリって結局、鉄

クロモリフレームの「クロモリ」って
「クロム」と「モリブデン」という物質をスチールに添加したもの(ほかにもいろいろ入っていますが)。
添加の割合は下記の通り。
- 鉄976g(97.6%)
- クロム10g(1%)
- マンガン5g(0.5%)
- 炭素3g(0.3%)
- ニッケル2.5g(0.25%)
- モリブデン2g(0.02%)
- リン・硫黄0.5g(0.05%)
出典:いしやんロード
結局ほぼ鉄。
鉄でできたパイプをつなぎ合わせていく。
パイプ同士が隙間なく接合できるように、ドリルでカットしていく工程は見事。
フレームビルダーが、一つ一つ仕上げていく。
作業工程を見ると、欲しくなってしまう。
カーボンフレームの登場

自転車をそれほど知らない人でも、一度は耳にはしたことがあるツール・ド・フランス。
そんな有名なレースでも、余裕で使われてた。
グレッグ・レモンというアメリカのトップ選手が、次々と新しい機材を投入した1990年辺り。
「TVT」というアルミラグにカーボンパイプを接着した画期的なフレームが登場。
その後、
極太肉薄フルアルミ時代
↓
アルミメイン三角に、シートステーのみカーボンのハイブリット時代
↓
現在のフルカーボンモノコック時代
これ以前が、クロモリ時代。
ここ最近自転車に興味を持った方なら、信じられないかも。
アルミラグにカーボンパイプを接着剤で接合していた時代。
発想自体はクロモリフレーム製作と同じだった。
この方法のメリットは、ミリ単位でサイズを調整できること。
パイプ長を調整できるのは、クロモリフレームと同じ。
しかし、この方法には問題があった。
アルミとカーボンの接合部分に電位差が生じて腐食の原因になることが分かった。
やがてこの工法は消滅。
実はすごいクロモリ

ツール・ド・フランスの総距離。
2019年は3480㎞。
30年程前は約4000㎞。
もっと昔はもっともっと長い。
もちろんピレネーとか、アルプスだって超えた。
その当時のレースに、現代のホビーライダーがタイムスリップして、カーボンバイクで挑んだとしても勝てない。
クロモリフレームはレース機材じゃないなんて、大ウソ
ホビーレースにクロモリバイクで出場した時、会場で言われた。
「よくクロモリなんかで集団にいれますね。すごいですね」
カーボンフレームが、飛び道具のような情報発信は実に罪深い。
でも、工業の世界は新しいものを作って、売らなければメーカーが食っていけない。
市場も大きくならない。
これが新商品が出る仕組み。
だから、今ではクロモリフレームと言えば、一部の自転車オタクが楽しむもの。
そんな位置付けが色濃くなってる。
価格は20~30万円と言ったところ(もっと高価な工房もあるけど)。

そんなに高いの?だったらカーボンにするよ
そうなってしまうのも無理はない。
でも、原価の内訳の大半はこんな感じ。
- カーボンフレーム→設備費
- クロモリフレーム→人件費
さらに、プロチームに供給しているような有名ブランドの価格に含まれているもの。
それは莫大な広告費。
そんなカーボンフレームを作っているのは、職人じゃなくて作業員。
一日に何台できるんだろう。
流れ作業で効率よく作られていく。
すごい設計と、すごい開発をしているのは想像できる。
でも、実際に作るのは自転車に何の興味もなさそうな人たち。
淡々とぺたぺたカーボンシートを貼っている姿を見ると、
「やっぱり、ほしいのはこれじゃない」ってなっちゃう。
関連記事>>>【クロモリフォーク】今さらクロモリフォーク選んだその理由とは
クロモリ初心者におすすめするブランド3選
カスタムフレームを製作している工房は、意外にたくさんある。
でも、ベースは競輪フレームを作ってるところが多い。
だから、新しい工作やパイプを使って作ってくれるところは限られる。
その中でも、クロモリ初心者が手をだしても大丈夫そうなブランド3選がこちら。
スチールフレームを骨董品にしないTOYO(トーヨー)

全日本シクロクロス選手権を、5連覇した竹ノ内選手が乗っていたブランド。
スチールフレームが、今でもレース機材であることを証明してくれた。
決まったサイズの商品もあって、勉強しなくても大丈夫。
元々はOEM工場だけあって、製作本数とか経験値はすごい。
めっちゃオシャレなMADMAN

アメリカンバイクカルチャーに大きく影響を受けている工房。
超おしゃれなバイクに仕上がること間違いなし。
シートステーなんて、じっくり見ていても飽きないぐらい美しい曲線。
パイプのつぶしも、一方向だけじゃない。
各方向から、剛性やクリアランスを計算されてつぶされている。
でも、作り手のこだわりが強すぎて、好き嫌いが分かれるところ。
関西の老舗ブランド、エクタープロトン

長い歴史があり、信頼度は抜群。
おそらく相当な数を作っている。
ものづくりに一本やりなのが熱い。
Tig溶接が得意なので、比較的軽量に仕上がる。
国内のフレームビルダーは、競輪フレームが主な収入源。
競輪フレームと言えば、ロウ付け。
パイプとの接合はラグを用いる。
だから重量的には不利。
Tig溶接なら、ラグを使うことはなく比較的軽量に仕上がる。
競輪の土壌があるので、Tig溶接のフレームビルダーは育たないらしい。
そんな中、割安で製作してくれるエクタープロトン。
関連記事>>>【ロードバイク】シンプルであることは尊い【クロモリ】【非ディスク】
デメリットもたくさんある

まずはデメリットから
ここを理解しないと、いい買い物ができない。
代理店を通す場合も、基本は職人が相手。
それは愛想のいい店員じゃないと言うこと
大衆向けの大量生産のカーボンフレームを売っている店員とは違う。
作り手にはこだわりがある。
カスタムとはいえ、自分の自由に作るというわけではなく、サイズが自由になるということ。
職人のこだわりと、自分の好みがマッチしたビルダーを選ぶのがコツ。
ショップの店員だと思って接すると、腹が立つこともあるくらい。
ある程度フレームのことがわからないと、相手の言っていることがわからない。
「ここをこうしたい」というのがあるから、カスタムすることが前提。
だから、かならず質問がある。
その質問を理解して、答えられる必要がある。
でも、ここがカーボンフレームを買うのと違うところ。
誰もが気軽に買えないところに、醍醐味がある。
重いよ
基本的に軽く作ったら、剛性が損なわれるのがクロモリ。
でも、カーボンフレームとの重量差は、前の日に食べすぎちゃったなというぐらいの差。
軽量オタクのヒルクライマーでなければ、気にすることはない。
そうは言っても、カーボンよりは確実に重いのは事実。
出来上がってきて愕然としないように。
体験談:
クロモリフレームに乗っている人でも、ほとんどはフォークはカーボンであることが多い。
だけど、フォークだけカーボンだと、そこだけすごく太くなる。
これが嫌で、シルエットをきれいにするために、フォークまでクロモリで製作してもらった。
が、これが強烈に重かった。かるくカーボンフォークの倍の重量はあった。
急いで、クランクをカーボンにしたり、シートポストをスカンジウムにしたりと、軽量化を図った経験がある。
でも、フォークまでクロモリであることが、強烈な個性を放った一台になった。
ホビーレーサーだからこそ生かせるメリット
サイズが自由になる。
今の不満を解消できる。
ステムを長くしたいなら、今のトップチューブより短く作ればいい。
シートピラーをもっと出したいなら、スロープをきつめにする。
まあ、無理がある形になってはまずいので、基本設計はあるけど。
取り扱いにもメリットがある。
カーボンだと、
壁に立てかけて休憩中
強めの風が吹いてパタンってなって
ポキン…
クロモリなら考えられない。
もし一部がダメになっても、修正やパイプ差し替えなんてこともできる。
例えるなら革製品のように
- 使えば使うほど味わいが出る
- 修理しながら長く付き合える
カーボンフレームには、こんな温かみはない。
目をギラギラさせて是が非でも、いいリザルトをとりに行くならカーボン一択かもしれない。
そうでないホビーレーサーなら、革製品のようなクロモリフレームは大人のたしなみ。
関連記事>>>カーボンフレーム不要論…先入観のワナ
サイズ以外、どこをカスタムできるのか
「オーダーフレーム」
これだとアマゾンでポチっと買った意味。
本来は「カスタムフレーム」。
最大の魅力は、カスタムできるところ。
例えば、
- ヘッドパーツをインターナルにするか、エクスターナルにするか
- シクロクロスだったら、クリアランス確保のためにつぶしを入れる
- ラグドか、ラグレスか
- シートピラー固定方法はバンドか一体型か
まだまだあるけど、こだわったのがココ。

前述のとおり、スチールフレームをカスタムする場合も、フォークだけはカーボンが一般的。
理由は、重いから。
出来上がったクロモリフォークを持ってみてびっくり。
1㎏…
軽量化に興味はない。
でもあまりの重さに、速攻でSRAM RIVAL アルミクランク装着を中止。
SRAM FORCEのカーボンクランクを発注。
でも、乗ってみるとコラム径1 1/8インチストレートカーボンコラムがなくなった理由がわかった。
カーボンコラムで1 1/8インチのストレートだと完全に剛性不足。
クロモリフォークだと、この径でも全く剛性不足感がない。
こんなに細いのに。

ゴツイ感じを出したくて、フォークの肩は「セグメント」を選択。
でも、これでさらに重くなった説もあり…

そしてヘッド。
要は、普通にヘッドパーツを買ってつける仕様ってこと。
エクスターナル⇔インターナル
ヘッドパーツが内装されているかどうかってこと。
写真は外装仕様の「エクスターナル」。
ヘッドパーツを別途購入することはないのはインターナル(インテグラル)ヘッド。
もはや、インターナル仕様が標準すぎて死語。
クロモリフレームならではのエクスターナルを選択。
エクスターナルにすることで、別途ヘッドパーツが必要になる。
だから刺し色が加えられる。
ヘッドチューブを短く依頼(写真参照)。
ハンドルを低くできるように要望した結果。
カスタムフレームだけの特権。

シートバンドも同色のブルー。
これも、シートバンドにしたいことを伝えないと、ビルダーの好みの仕様になる。

シングルギアしか取り付けられない、チェーンリングとチェーンステーとのクリアランス。
製作する際に、どのパーツを付けるのか聞かれたので、
「SRAMのシングルですねー」と軽く答えたら、まさかの完全シングル仕様。
カスタムバイクって感じ。
無駄のないところがいい。
まとめ
クロモリって鉄です
軽くて強い鉄はない
クロモリ初心者におすすめするブランド3選
ポチっと手に入らないおもしろさ
デメリットもたくさんある
同じ自転車でもカーボンとは生産工程が全く違う
「オーダー」じゃなくて「カスタム」
家と一緒で2台目が理想のフレームになるかも
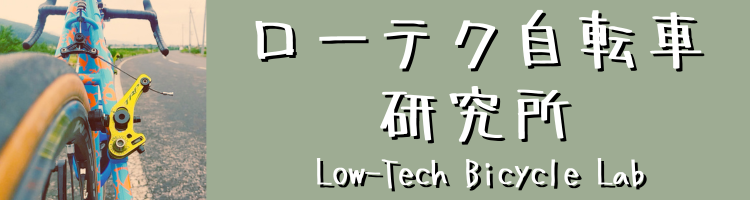
コメント
Hello, I like your site very much. The content was very helpful. I will visit your site more often now.