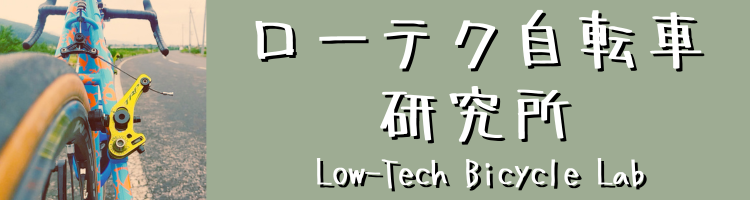みんなカーボンフレーム乗ってるけど、そんなに違うもん?

そりゃ、踏んだときスッと前に進んでくれるとかさー、あれだよ、あれ…
疑問
それ、ほんとに感じてる?
正直、フレームの乗り味ってそんなに違うの?
インプレッション記事にありがちな表現。
- よく前に進んでくれる
- 振動吸収性がいい
- 反応がいい
- 突き上げてくる感じが少ない
- BB周りのしなりが心地いい
その記事を読んで、期待に胸膨らませて買ってみる。
いままでのバイクとは、全然違うはず。
グイグイすすんじゃって、もーどうしよう。
疲れ知らずの100㎞になっちゃうなー。
が、実際乗ってみると…

なんか別にフツー…考え事してたら、バイクが変わったことすら忘れる
新しいバイクを買ったから、何か違うところを探したい。
どこかが違うはず。
だから、インプレッション記事と似たような印象をもってしまう。
先入観の恐ろしいところ。
自分に正直になる。
実は、驚くほどの違いないんてない。
高価なカーボンか、安いアルミにするか迷っていたら、それは時間とお金の無駄。
結論
安いので十分
自転車を楽しむなら、本質的なところはもっとほかにある。
高価なバイクには、たっぷり広告費がのっかっている。
流されてはいけない

比べた末の発言

違いを検証するなら、対象となるもの以外すべて同じものにする必要がある
これは現実的でない。
空気圧がほんの少し低いだけで、路面からの振動の伝わり方は違ってくる。
なのに、比べられるバイクのパーツがいろいろ違うのに、2台の差を感じるのはかなり困難なはず。
思い込みは恐ろしい。
自分が得た情報によって、感じ方を左右される。
- プロ選手が使っている
- インプレッション記事で評判がよかった
- ショップ店員がすすめてきた
これらが先入観を呼び込む。
どれもみんな、ネガティブなポイントを伝えてくれるわけがない
バイクの違いが及ぼす走りの影響はある。
理論上は。
が、エンジンはあくまで自分。
体調次第で、すべてが変わる。
最先端カーボンバイクなら速いかもしれない。
現実は、その影響力はほぼない。
初心者、ホビーレーサーにはまるでない。
限界まで鍛え上げられたプロ選手なら、その違いは影響大。
まず初心者にとって、大事なのは自転車に乗ること。
機材云々ではない。
必要性の見極め
自分にとって、それが必要かどうかを考えるのはすごく大切。
趣味の前に、生活がある。
100万円の自転車を買うことは、冷静に考えて自分と釣り合っているのか。
プロも乗る機材に乗ることは優越感がある。
これを逆説的に考えてみる。
カーボンフレームは金型が必要。
金型製作は多大なコストがかかる。
だから、プロ選手一人ひとりの要望に応えることはできない。
よって、プロ選手も一般人も同じものになってしまう。
これが、プロ選手と同じバイクに乗れるということ。
果たして、ホビーレーサーにトップスペックバイクが必要なのだろうか。
安いバイクでも十分に楽しい
必要性だけを追っていても、つまらないものになってしまうことも事実。
この境目を狙った賢い買い物が、趣味を長続きさせるコツ
乗り心地の差の実態

寸法の違い
車やモーターサイクルのように、乗ってすぐ違いがわかるのか?
それは違う。
わかるのはハンドリングぐらい。
コーナーを曲がっている時や、ダンシングしている時にハンドルが切れ込みやすいか否か。
これは各部分の寸法の違いからくるもの。
操作感が自分にマッチしないと、快適に乗れない。
これは、フレーム各部分の長さとか角度の問題。
例えば、ホイールベース(前後輪の中心を結んだ距離)の違い。
- 長い→直進安定性が高い
- 短い→曲がりやすい
この部分は比較的、違いを体感しやすい。
剛性感
「ちょっと自転車乗らせてー」
「えー、これすごいいいじゃーん。すすむねー」
実際、駐車場をちょっと乗ったぐらいで、わかることはほぼない。
ましてや、ペダルが違って、トルクをかけられないのに。
たとえば、剛性感を言うときに「BBがたわむ」「しなる」という表現が使われる。
でも、ある一定の力以上を伝えないと「たわむ」ことも「しなる」こともない。
だから簡単には、剛性感を感じることはできない
でも、インプレッション記事に出てきた表現を、使いたくなってしまう。
事前情報から、ほんとにそう感じてしまうのかもしれない。
きっと、事前情報によって感想が変わってくるのではないか。
実際の違いは、その程度。
プロ選手に30年前のバイクに乗ってもらっても、素人が勝てないのは明らか。
結局、人力だから
細かいことなんて気にしないほうが幸せ。
何に投資するか
動画はカーボンフレーム工場で、カーボンシートをペタペタ貼るところから始まる
高級カーボンと廉価アルミの利点
カーボンフレームは現在考えられるフレーム素材として、間違いない。
でも、製作工程は衝撃。
カーボンシートをペタペタ貼って…
そんなことないと思うけど、どうしても適当に貼っているように見える…
が、最先端のカーボンバイクは超軽い。
太くてなんか強そう。
ほんでエアロ。
買う前のイメージは、めちゃ早く走れそう。
しかし、そのメリットが、走りに影響を及ぼすことは少ない
そんな微々たる差は、例えばレース前夜の睡眠不足で帳消し。
体調不良の影響のほうが大きすぎる。
苦しい場面なんて、最先端バイクに乗っている事すら忘れる。
フレームの差って実際にはそんなもの。
だから、値段で迷っているなら安いほうを買うべき
10万円浮いたら、ウエアに投資。
そのほうが、よっぽど快適に走れる。
そして明らかな違いを体感できる。
例えば、
- 半袖と分厚い長袖しかない→春、秋用のウエアを揃える
- 分厚い冬用シューズカバーしかない→薄手のソックスシューズカバーの導入
- 無くても問題はないベストは持ってない→買ってみると超快適に走れる
あくまで、走っているのは自分であって、勝手に自転車が走るわけじゃない。
ウエアに投資するのは、エンジンに投資するのと同じ。
もっと自分自身に注目をしたほうがいい。
ホビーライダーならではの選択
スチールフレームは、職人がこだわりを持ってつくってる。
カーボンフレームの生産工程って、予想外で衝撃を受ける。
紛れもない単なる工業製品。
一日に何本できるのだろう。
システマチックに、ペタペタ、ガチャコン、ガチャコン、ジューって作られてる。
フレームビルダーが、一本一本作っているのとは世界が違う。
カーボンフレームは大量生産が大前提。
なぜなら莫大な設備投資が必要だから。
裏を返せば、そこに個性はない。
プロ選手なら、速さやコマーシャルの関係で最新の機材を選択せざる得ない。
でも、ホビーライダーなら別の選択肢もある。
フルカスタムのスチールフレーム
- BB下がりを何ミリにするとか
- フロント~センターを何ミリにするとか
- どんなカラー、どんなデザインにするかとか
通常、カーボンバイクを買うときには、ありえない選択肢。
大量生産じゃないものに触れる機会って意外に少ない。
一品ものは、愛着が沸く。
自転車好きが、一台一台丹精込めて作るモノって聞いただけでほしくなる。
金属だから、耐久性も高く長く付き合える。
一番の趣味だから、こんな選択肢もある。
先入観の実例

知人が、とてつもない高価なフレームを購入。
なんでも、前作よりも、さらによくなっていると豪語。

平均速度が2㎞もアップしたよ。ちょっと乗ってみろよ。すげーから
(プラシーボ効果ってこのことだな)
あまりにすすめるので、仕方なしに乗ってみる。
そもそもペダルが違うから、踏み込んだりできない。
サイクリストあるあるシチュエーション。
ペダルもハマってないのに乗り心地なんてわかるわけがない。
ホイールもタイヤもタイヤの空気圧も違う。
乗り味を比べるのは至難の業。
ところが乗った瞬間、サドルのボルトが緩んでガタガタであることが判明。
パーツがまともに取りついていないことには気づけない。
でも、フレームの乗り味はわかっちゃう。

まさに先入観
- フレームが新しくなった⇒どこか違っているはず
- サドルは緩んでいない⇒しっかり取り付けてもらった
感じ方は、先入観しだい。
まとめ
トッププロはフィジカルの差が接近してるから、フレームの良し悪しによって成績が影響する。
そもそも、ホビーライダーはスキルやフィジカルに大きな差がある。
高級カーボンフレームに乗ったところで、10位が9位になることはない。
フレーム性能の違いが及ぼす走りへの影響はわずか。
シンプルにカッコいいと思ったものを買うべき。