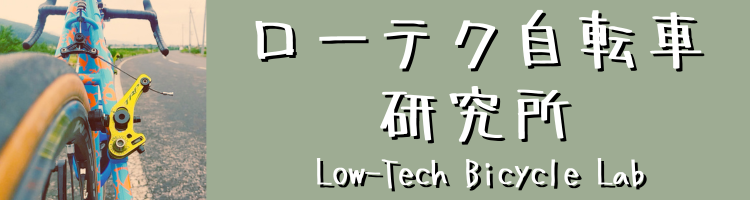もっと華麗にバリアー(シケイン)越えしたいんだよね

それなら、やっぱバニホじゃね?
シクロクロスといえば、特徴的なのがバリアー(シケイン)。
実はバリアーと呼ぶのが正しい。
突然、コース上に高さ30㎝、コース幅いっぱいの板が現れる。
自転車から降りたり、ジャンプしないと越えられない。
バリアーは、やたら体力が削られる
滑らかに超えられると、体力を温存できる。
近年、プロの世界ではバニーホップが標準スキルになってる。
できるようになりたいけど、道のりは遠い。
しかも、練習で200%ぐらい成功しないとレースでは使えない。
心拍数が高い状態で、レース後半でもバニーホップができるのか。
多くの人には難しい。
トレーニング時間もたくさん必要。
しかし、社会人ライダーにとってトレーニング時間は限られている。
今日2時間トレーニングに使える。
バニーホップの練習に、この貴重な2時間注ぎ込むのか
仮にバニーホップが完璧になったとする。
が、しかし所詮バリアーはコースの一部でしかない。
もし、確実にできれば有利にはなる。
だが、その効果はかなり限定的。
さらに、どう考えても着地の際のフォーク、ヘッドチューブ周辺の負担が大きい。
毎年ニューバイクにするわけじゃないホビーレーサーには向かない技。
無駄が多いバニーホップはあきらめるのが正解。
バリアーは、きれいな降車、乗車フォームで乗り越える。
結局、これが最も速い。
それに安全。
バイクも傷めない。
ホビーレーサーがめざすもの
- 華麗な降車
- 無駄のない乗車
右足の使い方がポイント
乗車のコツ
シクロクロス初心者の境目は、乗車がうまいか否か。
乗車フォームの美しさは、観察力と練習量に比例する。
- 膝を高く上げる意識をもつ
- できる限り低くジャンプする
そして最大のポイント。
右足のソールを地面に向けたまま乗車できるか否か
初心者ほど、ソールが空を向いている。
乗車時に、ソールを地面に向けることを意識する。
そうすることで、ジャンプの高さも最小限に抑えられる。
サドル上面を滑るように乗車。
エネルギー消費を最小限に抑えつつ、バリアー越えできる。
最初はジャンプしなくていい。
バイクを押しながら歩いて乗ってみる。
案外ジャンプしなくても乗れることがわかるはず。
降車のコツ
トップチューブをつかんで、バイクを持ち上げるまで何歩か?
二歩
シケイン直前まで下りない。
二歩以上なら、降りるのが手前すぎる。
バイクから降りる時間が長ければ、失速するのは当然。
二歩でシケインに突入するには、トレーニングが必要。
バイクを持ち上げるタイミングが遅ければ、フロントホイールをバリアーに引っ掛けてしまう。
多くのライダーは、右足からペダルを外してすぐに降りようとする。
ここが上級者との違い。
- 右ペダルから足を外す
- 右足を車体左側へ移動
- 右手をハンドルからトップチューブに持ち変える
- バリアーに2歩で到達するタイミングまで3.の状態を保つ
- 左ペダルから足を外し、右足、左足の順で着地
- バイクを持ち上げてバリアー越え
最初は一つ一つをゆっくり確実に動作できるまで反復。
最後はレースと同等のスピードで、バリアーに侵入できるまでトレーニングする。
関連記事>>>【シクロクロス練習】意外と思いつかない練習方法【飛び乗りだけじゃダメ】
動画レッスン
シクロクロススターのレッスン動画
動画の講師はSven Nys(スヴェン・ネイス)。
シクロクロスで数多くの勝利を挙げた元プロ選手。
乗車時は、バイクを押して前に出す。
右足のソールはきっちり地面の方向を向いている。
ジャンプする高さは、サドルギリギリ。
見るからに無駄が無く、力づくの動作はない。
バリアーを越えると、心拍数が急にあがる。
息が上がり、相手と競り合いの場面なら、バリアー後に集中力が切れやすい。
いかに滑らかに、息をあげずに乗り越えられるかは、非常に重要。
練習量がものをいう。
国内のレースを見ても、バリアー越えに時間を割いている選手は皆無。
逆にチャンス。
スピードアップだけを狙うものでもない。
自分の体力を温存するためにも、技を磨くべき。
プロ選手を観察
日本だとマイナースポーツの自転車競技。
プロ選手にあこがれて始める人は、非常に少ない。
だから、プロ選手がどんなフォームをしているのか気になる人も少ない。
でも、一番のお手本はプロ選手。
よく観察して、細部までまねることでフォームがよくなっていく。
サッカーや野球なら当たり前の練習方法も、自転車競技になると急に視野が狭くなる。
よくあるのが、自分の周りにいるサイクリストを参考にしてしまうこと。
その人が独特なフォームだった場合、独特が連鎖する。
実は、だれもそんなフォームで走ってない。
なんて事態になりかねない。
是非とも参考にするのはプロ選手にしてほしい。
シクロクロスもUCI公式チャンネルで配信されている。
じっくり観察して、イメージを完成させると上達が早い。
関連記事>>>シクロクロスのおすすめ準備品!
練習量がものをいう「担ぎ」
動作のスピード
シクロクロスは、しばしば階段が登場する。
手段は二通り。
- トップチューブを持ち上げる
- 担ぐ
車体から身体が離れれば離れるほど、不安定になる。
だから担いで登ったほうが、安定する。
短い登りなら、トップチューブを持って走ったほうが速い。
足場がわるかったり、長い階段なら担ぎが有利。
しかし、担ぎの練習が不足していると選択肢が狭まる
- 担ぎの動作がもたつくことが頭によぎる
- 担ぎが選択肢から外れる
- トップチューブを持ち上げる方法一択になる
不安定な走りを強いられる。
エネルギーも余分に消耗する。
バイクを肩に掛けるまでの動作が、速ければ速いほど対応力に差が出る。
エネルギーをセーブすることにつながる。
担ぎの練習時間をしっかりと用意することが重要。
右腕の動きの違い
担ぎ方には2種類ある。
Wout van AertとMathieu van der Poelは、それぞれ担ぎ方が違う。
動画を見てほしい。
Wout van Aert
- トップチューブをもって担ぎ上げる
- 右腕はヘッドチューブ前方に回っている
Mathieu van der Poel
- ダウンチューブをもって担ぎ上げる
- 右腕はダウンチューブ下を回っている
ダウンチューブを持ち上げる方法
メリット:バイクの重さを感じにくく、動作が小さくて済む
デメリット:泥のレースの場合、手に泥が付いてハンドルを持ったとき滑る
トップチューブを持ち上げる方法
メリット:泥が手に付かないので、ハンドルを持っても滑らない
デメリット:動作が大きく、習得には練習量が必要
国内でトップチューブを持ち上げる方法とる選手は少ない。
しかし、泥のレースでは手に泥がつかないメリットは大きい。
担いだ後のハンドル固定方法にも、違いがある。
いろいろな方法を試して、速く確実な動作ができる方法を確立したい。
まとめ
右足の使い方がポイント
右足を意識するかしないかで、エネルギー消耗が全く違う
動画レッスン
プロ選手を観察し、イメージする
練習量がものをいう「担ぎ」
練習量をこなして、動作のスピードを上げる